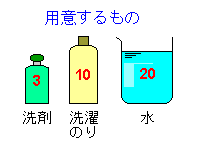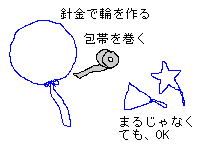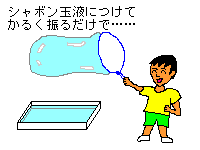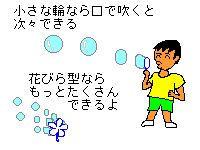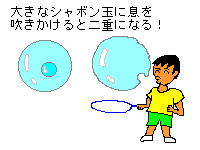シャボン玉日記 0
おまけ、っていうか、まとめのページ
長々とシャボン玉日記を綴ってきたが、苦労話には飽きが来るもの。
そこで、ここでは巨大シャボン玉の作り方のエッセンスのみを書き出した。
ご家庭で、あるいは学校やサークルでの活動のお役に立てれば幸いである。
シャボン玉液の作り方
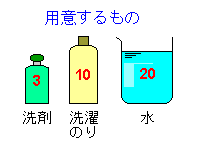
左の図に示した通り、洗剤と洗濯のりと水を用意しよう。
洗剤は、濃縮タイプと呼ばれるミニボトルのものがよい。
メーカーや製品によっても出来がちがうようである。
私達は、ライオンのママポケッティ1/2を使った。
洗濯のりは、PVA(ポリビニルアルコール)製の液体のりがよい。
乳液タイプというのもあるが、試したことがないので何とも言えない。
たぶん無理。
水は、たぶん精製水がよいと思う。
水道水でもそれほど悪いとは思えないが、念のため。
私達は実験用の純水製造装置を使って脱イオンした蒸留水を作っているので、それを使った。
高専の役得である。
問題は混ぜる割合だ。
日記を読んでいただければわかるが、これなら完璧、という組成をまだ会得していない。
気温や湿度といった外部要因も影響してくるので複雑なのだ。
しかし、今のところ、洗剤:洗濯のり:水=1:3.3:6.7、うーんわかりにくいな、洗剤:洗濯のり:水=3:10:20の割合が最も信頼性が高いことがわかっている。
【2006年夏時点での新情報】
2001年以降、諸事情によりしばらく巨大シャボン玉作成から遠ざかっていたが、その間に大きな変化があったらしい。
市販洗剤の成分が変わってしまったのだ。
どうやら、泡切れをよくする成分が導入され、これまでの組成では人が入れるほどの巨大シャボン玉ができなくなってしまったという。
2004年に愛媛県総合科学博物館の科学クラブに所属する方にお話する機会があり、そのことを知った。
ところが、2006年にとある情報を得て、ある洗剤を試してみると、なんと洗濯のりなしで十分人が入れる巨大シャボン玉ができたのだ。
その洗剤とはライオンのチャーミーVクイック。
これを10〜20%程度に水で薄めてやるだけ!
薄める割合は、やはり温度や湿度によって変わるようだ。
これを泡立てないように十分混ぜる。
洗剤も洗濯のりもかなり粘っこいので、混ぜたつもりでもむらが残りやすい。
私達はマグネティックスターラという、短い磁石の棒を回転させて液を混ぜる装置を使って1時間撹拌した。
ハンドミキサーみたいなものでもいいと思うが、空気を巻き込んで泡立つことのないようにだけ注意したい。
シャボン玉作成器具の作り方
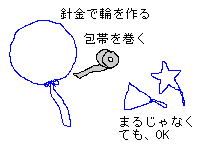
大きなシャボン玉を作るためには簡単な器具が必要である。
左の図のように、針金を曲げて輪を作り、これに取っ手をつければよい。
いらなくなったハンガーを変形させてつくるのも一つの手だ。
これだけでも結構うまくできるが、さらに輪の部分に包帯を巻くと液が染み込んで長持ちし、大きなシャボン玉ができやすい。
取っ手に包帯を巻くと液が染みて手が濡れるので、ここは巻かないこと。
持ちにくい場合はビニールテープを巻いてやるとよい。
輪の形は円でなくても大丈夫だ。
三角や四角はもちろん、星型などでもきれいにできる。
ただし、できるシャボン玉は球形にしかならないけどね。
シャボン玉の遊び方
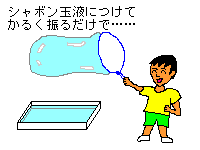
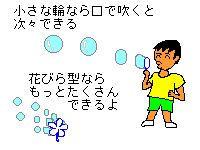
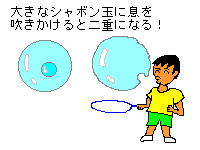
遊び方など自由であって、教える必要はまったくないのだが、ちょっとした裏技紹介も含めてひとくさり。
基本は左上の図のように、輪っかをシャボン玉液につけてかるく振るだけ。
シャボン玉の大きさは輪の大きさによって違う。
液がうまくできていれば、直径70〜80cmのものもきれいにできる。
風のある日は手を動かさなくてもどんどんできるけど、風向きに注意。
小さな輪の場合、中上の図のように息を吹きかけると、小さなシャボン玉が次々にできる。
手で振ってやっても、うまくするとたくさんのシャボン玉ができる。
ちょっと、こつがいるかな。
輪を花びら型にすると、いくつものシャボン玉を同時に作ることもできる。
二つのシャボン玉がくっついた双子もつくれる。
いろいろな形を工夫してみよう。
大きなシャボン玉ができたら、右上の図のように息を吹きかけてみよう。
うまくやれば二重のシャボン玉ができるぞ。
シャボン玉液があまりよくないとはじけてしまうけれど、うまくできていれば大丈夫。
1つのシャボン玉に何個小さなシャボン玉を入れることができるだろうか。